頑張ってもできないことがある。それが障害だと思う話

今回の記事を書くのは、
令和6年1月に、**自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如多動性障害(ADHD)**と診断を受けた、トイプードルの私です。🐾
平日はまったりマイペースに過ごしつつ、
休日は嫁と一緒にカフェでのんびり過ごす時間が何よりの楽しみ!
障害があっても、できることをひとつずつ大事にしながら、
ちょっと笑えて、ちょっと役に立つ、そんな記事をお届けできたらと思っています。

特性のこと、私生活のこと、そして“周りの理解”のこと。
こんにちは。最近、少しずつ自分の心の中を整理しながら過ごしています。
私は自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠如多動性障害(ADHD)があります。
日々、自分なりにがんばってきたつもりですが、最近は改めて「がんばる」ということの意味を考え直しています。
自己理解はあっても、周りからの理解は難しい
自分の特性についての理解は進んできました。
感覚の過敏さ、マルチタスクの苦手さ、環境の変化への適応の難しさ。
私はそれらをひとつひとつ受け入れてきました。
でも、定型発達の人たちからの理解は、やっぱり難しいと感じています。
空気を読むこと、臨機応変に対応すること、相手の意図をくみ取ること。
これらを自然にこなす周囲の中で、私は「そこが苦手なんです」と言い出しづらく、
それでもできないと「特性を言い訳にするな」と見られてしまうこともあります。
障害とは「頑張ればできる」ことではない
障害というのは、「頑張ればできること」ではありません。
頑張ってもできないことがあるからこそ、“障害”なのです。
それでも、私を含め多くの発達障害のある人は、「迷惑をかけたくない」と考え、
周囲に合わせようと過剰に努力してしまうことがあります。
その結果、心身の不調をきたすことも少なくありません。
私自身も、これまでに動悸・嘔吐・睡眠障害といった二次障害を経験しています。
これは、ASD・ADHDを抱える人によく見られる症状でもあります
(参考:法務省さいたま地方法務局 発達障害と職場の配慮に関する資料)。
自己分析ができるからこその苦しさもある
私は自己分析が得意な方だと思っています。
だからこそ、「自分はこういう場面が苦手」「これはどうしても無理」と気づける一方で、
周りと同じようにできない自分を責めてしまうこともあります。
でも最近やっと、「それでいいんだ」と思えるようになってきました。
周りと同じようにできないことを受け入れること。
それは、自分自身と障害を受け入れることであり、
その先にあるのは、少しだけ楽に生きられる毎日だと思います。
一人でがんばらなくていい、つながることで救われる
私は今、同じ悩み(障害)を抱える人たちとつながることで、なんとか自分の居場所をつくっています。
「話せる人がいる」「わかってくれる人がいる」と思えるだけで、
毎日を過ごす気持ちがずいぶん変わってきました。

最後に
発達障害があると、見た目では伝わりづらい困難が多くあります。
でも、それを「なかったこと」にするのではなく、
声に出せる社会、理解し合える関係が少しずつでも広がっていくことを願っています。
そして今日も、私は私なりのペースで、生きていこうと思います。
-
Previous article

「私だけじゃなかった」|聞こえにくさを語れる場所に出会って 2025.04.26
-
Next Article

聴覚障害ママの子育て記録|2歳半の息子とことばでつながる日々 2025.04.28




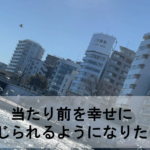

Write a comment