人の気持ちがわからない私が、国語で1位だった理由 〜ASDと国語の“矛盾”じゃなくて“独自性”の話〜
- 2025.05.10
- 凸凹のつぶやき
- ASD, 凸凹フレンズブログ, 国語が得意, 感情の読み取り, 発達障害と勉強, 自分らしい学び方, 自閉スペクトラム症, 視点の違い, 言葉と共感, 論理的共感
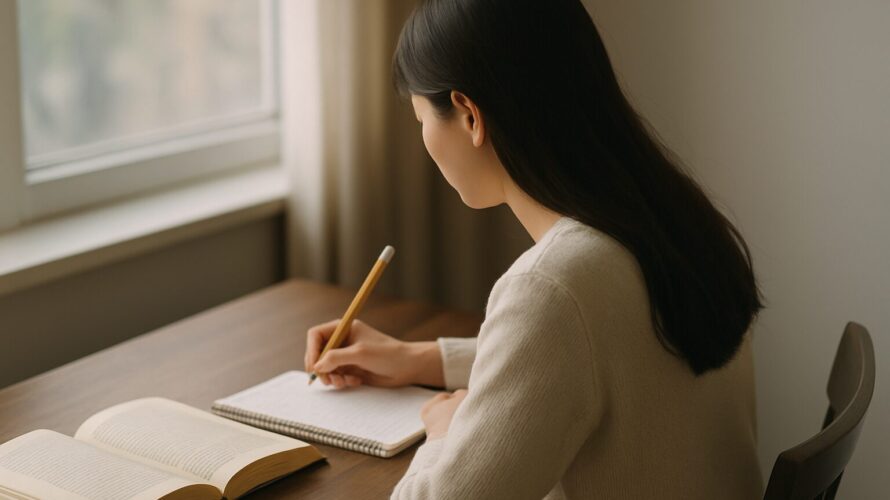
人の気持ちがわからない私が、国語で1位だった理由
〜ASDと国語の“矛盾”じゃなくて“独自性”の話〜
はじめに
発達障害(ASD・ADHD・双極性障害)をもつ、みったんです。
「凸凹フレンズ」の代表をしています。
趣味は歌・ギター・知識を増やすこと・たくさん笑うこと。
このブログでは、自分の凸凹をありのままに言葉にしていきます。
「人の表情を読むのが苦手」って本当?
──ASD(自閉スペクトラム症)の説明で、よく出てくる言葉。
でも正直、それが自分に本当に当てはまるのかどうか、私にはよくわからなかった。
だけど、
- 「人の気持ちがわからない」
- 「空気が読めてない」
- 「思っていることと違うふうに伝わってしまう」
そんなことを言われた経験は、何度もあった。
なのに、私は国語で1位だった
私は、塾の国語でずっと成績1位だった。
記述問題も、抜き出し問題も得意だった。
駿台模試で冊子に名前が載ったことだってある。
──ねぇ、どうして?
「人の気持ちがわからない」って言われてるのに、
どうして小説の中の人の気持ちは、あんなに読み取れたんだろう?
現実の感情は“流動的でノイズが多い”
現実の世界では、人の気持ちは
表情、声のトーン、沈黙、間、言葉の裏側に隠れている。
でもそれって、私にはものすごく“曖昧”で、正解がないように感じた。
だから、誤解されたり、傷つけたり、傷ついたり。
普通のやりとりの中で、ちょっとした一言の裏を読み違えて、
人間関係がこじれてしまうこともあった。
👉 実際に私が言葉のすれ違いで傷ついた話は、こちらに書いています
→ >「障害」と生きるって、どういうこと?|私が選んだ“逃げながら生きる”という道
小説には“ヒント”があるから読めた
小説の中には、「ヒント」が書いてある。
「彼女はうつむいた」
「声を震わせながら言った」
そういう描写があると、私は思う。
**「あ、この人は今、こう感じてるんだな」**って。
たぶん私は、感情を“感覚”じゃなく、“構造”として読み取っていた。
現実のように「今この場で感じて」と言われると分からないけど、
小説のように書き言葉で整理された情報なら、
論理的に、丁寧に、人の気持ちを想像することができた。
共感は“感覚”じゃなく、“理屈”で届いていた
「共感力がない」と言われたこともある。
でも、私はそうは思わない。感情がゼロなわけじゃない。
ただ、リアルタイムの感情キャッチはすごく苦手で、
逆に、言語情報として整理されていたら、“論理的な共感”ができた。
だから、国語の記述問題で「なぜ登場人物はこうしたのか?」と問われたとき、
私の頭の中では、感情と出来事が“因果関係”としてつながって、
それを丁寧に言葉にできたんだと思う。
👉 私が「共感がうまくできない」と悩んでいた時期のことは、こちらにも書いています
→ 大切な人へ|伝えきれない感謝を込めて
最後に
ASDだからこそ、“空気を読む”のは苦手かもしれない。
でも、“言葉で整理された世界”の中では、
誰よりも深く、誰よりも繊細に、人の気持ちを考えることができる。
それが、私の「国語1位」の理由だったのかもしれない。
「ASDなのに国語が得意」──それは矛盾じゃない。
ただ、“読み方が違う”だけだったんだ。
-
Previous article

「障害」と生きるって、どういうこと?|私が選んだ“逃げながら生きる”という道 2025.05.09
-
Next Article

母の日に寄せて|母に伝えたい「ありがとう」 2025.05.11






Write a comment